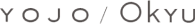團十郎もぐさ
歌舞伎にも「もぐさ」
“もぐさ せいほうもぐさ・・・
御ひやうばんにあづかるせいほうもぐさ。
外に此るいあまたごされど。かんだかぢ町壱丁めのしんみち。
みますやひやご。市川團十郎もぐさ。かつて下さい。めしませい。”
宝永6年(1709)二代目團十郎は江戸・山村座の「けいせい雲雀山(ひばりやま)」においてもぐさ売りを初演し大当たり、出世作となったのです。
━江戸時代のお灸事情
江戸時代になると、お灸は民間療法として広く用いられるようになりました。
そして「もぐさ」を1回分ずつ小分けにして、使いやすくした「切もぐさ」が誕生し、その便利さから、お灸の人気はいっそう高まり、江戸の町にはあちこちに「もぐさ」を売る店が誕生しました。
なかでも人気だったのが神田鍛冶町の「三升屋(みますや)」でした。
「切りもぐさ」に人気の團十郎の名を借りて「團十郎もぐさ」と名づけ、店の屋号も市川家の家紋から「三升屋」としたアイデアが大当たりしたのでした。

━二代目團十郎のもぐさ売り誕生
当時、江戸の町では、モノ売りの口上や、せりふで夜が明けるといわれるほどモノ売りが多く、その口上やせりふがしばしば町の話題になっていました。
早口のセリフ回しの面白さを生かしたもぐさ売りが完成し、2代目團十郎の人気は不動のものとなりました。
これを契機に歌舞伎には、モノ売りの演目が次々と登場するようになったのです。
そして、このもぐさ売りの成功は、後に市川家のお家芸として定めされた歌舞伎十八番に、『助六(すけろく)』『勧進帳(かんじんちょう)』『暫(しばらく)』などの荒事と並んで唯一入っている早口でまくしたてるせりふ芸が人気の『外郎売(ういろううり)』の誕生へとつながったのです。

━『せりふ正本』の誕生
二代目團十郎のもぐさ売りは、そのせりふの面白さが評判となったことから、團十郎のせりふを抜書きして、読み物とした『せりふ正本』まで出版されることに。
そして『せりふ正本』は以後、歌舞伎興行に欠かせないものとなったのです。
━千両役者は團十郎から
二代目團十郎の人気は絶大で、年間の出演料が千両にも達する役者であったことらか、千両役者と呼ばれるようになったとされています。
千両役者のことばまで生みだしたもぐさ売りは、二代目團十郎に新しいジャンルをひらかせ、その人気を不動のものとしたのです。
“むかふ三がい中さじき。下さんじき。ひとだまりのかたぐにも。一かはらけづゝ。
かつてもらわねばならぬ。ゆみや八まん大ぼさつ。ほゝうやまつて。
もぐさ。いらしやりませんか。”