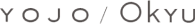お灸事典
お灸の記録


「火口」とは
「ほくち」は漢字で「火口」と書き、その字の示す通り、火が生まれる時に欠かせないものです。
火打石を火打金で削るように打ちつけると、一瞬にして火花が飛びます。
この火花をうけとめ種火にするために、乾燥した草や苔などが「火口」と呼ばれてきました。この「火口」に「もぐさ」はとても火つきがよく重宝されてきたのです。
火の歴史は人類の歴史
人の文化は火を使うことから始まったといわれています。
食べ物を美味しくしたり、カラダを温めたり、夜を明るくするなどの働きがあることを知り、人は火を利用することを考えました。
何十万年も前に始まったとされる火を使う歴史は、日本でも縄文時代や弥生時代の遺跡から火打石などが出土しており、その歴史を物語っています。


『和漢準源氏かがり火日本武尊』所蔵:静岡県立中央図書館
火をつくる
そして、いつでも火が使えるようにするために、人は自らの手で火をおこすことを始めました。
火をおこす方法は、大きく分けて2つあります。
今も神社で新年や祭事に新しい火をつくり出す方法として、火きり臼(ひきりうす)と呼ばれる厚板に、火きり棒と呼ばれる木の棒をキリのようにこすりあわせ摩擦熱で発火させる方法と、火打石と呼ばれる石と火打金を打ちつけるとび出す一瞬の火花を「火口」で受けとめ、火種にして火をおこす方法です。
ヤマトタケルの神話には、この火打石を使って火をおこし、野に放たれた賊を退治したという話が残っている通り、その歴史はとても古いのです。
「火口」の役割
しかしこの火打石を使った発火方式には、ひとつハードルがありました。というのは、火打石に火打金を打ちつけ飛び出した火花を瞬時に受けとめ、火種にするため、火つきがよく燃えやすい「火口」となるものが必要でした。あらゆるものが試されました。
ススキやガマの穂、乾燥した木の葉や木の皮など、なかにはアザミに似た花をつけるオヤマボクチと「火口」の名のある草もありました。


「もぐさ」が「火口」に
2000年もの昔からお灸に使われてきた「もぐさ」の語源は「燃え草」、よく燃える草。
「よもぎ」を乾燥してつくる「もぐさ」は、火つきよく火持ちよしがよいとされ、お灸に欠かせないものです。この特徴こそ、火花を確実にキャッチする「火口」にはまさにうってつけだったのです。
火打袋登場
そして、「火口」の発見により火花は実用的な火になりました。
やがて火打石と火打金そして「火口」の発火3点を小型化し、一つの袋に入れて携行できるようにした「火打袋(ひうちぶくろ)」が誕生するなど、火は自在に作ることができるようになりました。
明治時代になってマッチが普及するまで、長い間この「火口」によって実用化された火は、人々の暮らしを支えつづけてきたのです。

火打袋
「火打石一式」所蔵:静岡県立中央図書館
「火打袋」出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)