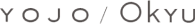お灸事典
お灸を愛した偉人

“春夏秋冬 灸をすえて、病気にならないよう常常心がけよ”
第3代将軍として、200年続く江戸幕府の基礎を築いたといわれる徳川家光。祖父の徳川家康は自分の幼名である竹千代の名を与えるほど、孫である家光の誕生を大いに喜んだと伝えられています。

しかし、家光は生来の病弱で、3歳の時に医者もさじを投げ出すほどの大病にかかるものの、家康が調合した薬で奇跡的に回復をとげたとか。また、家光の父・徳川秀忠が家光の弟である国松に家督を継がせようとした時も、家康自らがこれを阻止し、家光を3代将軍にすると決めたこともあり、家光は終生、家康を崇拝したといわれています。
常に家康を尊敬した家光ですが、祖父と相反することがありました。それがお灸。
家康はお灸嫌いで知られていますが、家光は大のお灸愛好家。
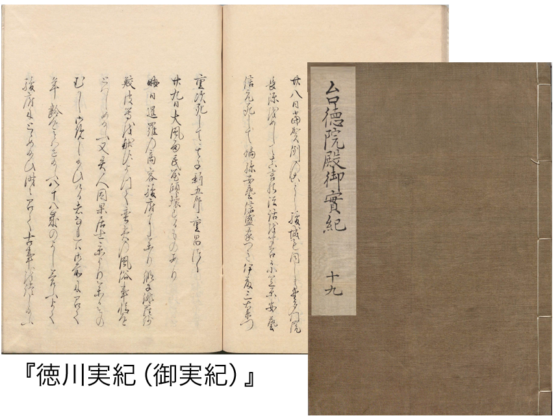
“九日、三卿諸大名出仕す。この日春日局生身魂の御膳を献ず。また御灸あり。”
“十一日、尾水両卿諸大名まうのぼる。御灸あり。”
“十二日、大名登営す。御灸きのふに同じ。”
江戸幕府の公式史書『徳川実紀(御実紀)』には、家光が毎日のようにお灸をした様子が記されており、いかに家光がお灸をするひとときを大切にしていたのかがうかがえます。
また、家光がお灸を好んだことが影響したのかも?と思わせる法令が、ちょうど家光の時代に発令されています。それは、慶安2年(1649)の家光の時代に江戸幕府が発令した、農民に対する決まり事を定めた文書「慶安御触書(けいあんのおふれがき)」(※現在は幕府法令がどうかは諸説あり)のこと。その中にはこんな一文が登場します。
“春秋灸をいたし、煩候ハぬ様ニ常ニ心掛へし、何程作ニ精を入度と存候ても、煩候てハ其年の作りをはつし、身上つふし申ものに候間、其心得専一なり、女房・子供も同然の事”
「春夏秋冬 灸をすえて、病気にならないよう常常心がけよ。どれほど農業に励もうともしても、病気になってはその年の生産が上がらず、財産をつぶすことになるから、お灸をすえるという心がけは大切であり、女房子供もおなじことである」
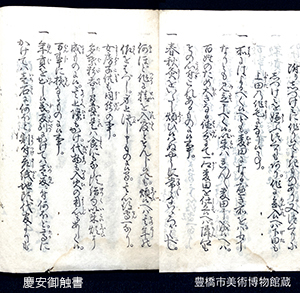
その内容は、お灸を毎日の暮らしに取り入れよという市井の人々の健康を思いやる法令です。その背景にはお灸の大切さを実感する家光の時代の空気が反映されているようです。
徳川家光像:東京大学史料編纂所所蔵
『光将軍徳川家累代像附累系』東京都立中央図書館 所蔵